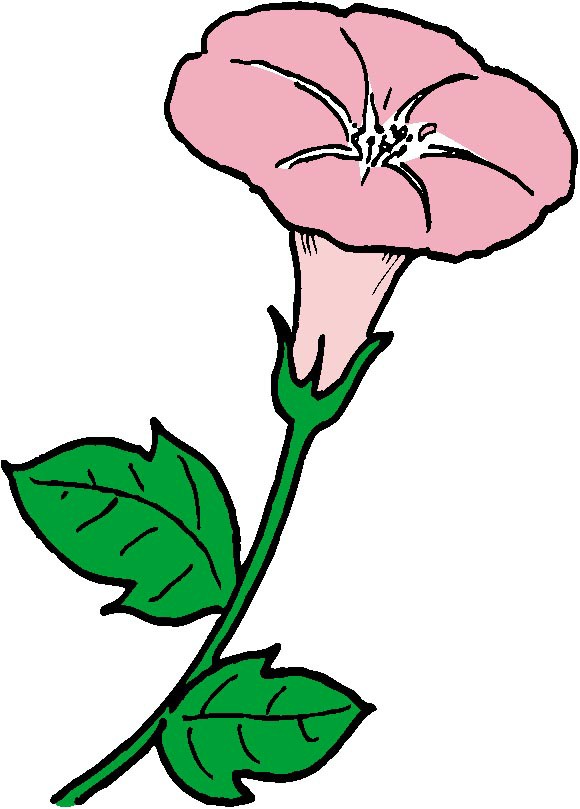がまん強い一粒の種のアサガオからはらはらと露のなみだがこぼれました。そうです。本当にがまん強い者にこそ、はげしく胸の底から泣かないではいられないときがあるのです。
いったい、どうしたというのでしょう? そうして、彼の露のなみだにはどんな思いがこめられていたのでしょうか? ではそのお話をしましょう。
ふくろの表には大きな赤いアサガオの絵が描いてありました。そうして、紙ぶくろのなかには、大勢のアサガオの種たちが入っています。ふくろは種たちがこぼれ出ないようにかたくのりづけしてありましたので、ふくろのなかはほとんど暗ヤミのじょうたいでした。暗ヤミのなかで種たちはお互いを「兄弟」とか「同じふくろのネズミ」とかいい合って、たいへん仲よく暮らしていました。
ところがある日のこと、とつぜん、ふくろの口が破かれ、種たちの上にサッとまぶしい光がさしこみました。種たちにとって、ふくろのなかのせまい世界から、広いほんとうの世界に出るときがきたのです。
明るく種たちは叫びました。
「オー・マイ・サンシャイン!」「まぶいよぉ!」
みんな新しい世界への希望に胸をふくらませました。ちょっぴりの不安もいっしょに・・・
パラパラと花壇のやわらかい土の上に種たちはまかれます。その上にそっと土がかぶせられ、そうして、じょうろでていねいに水が注がれます。やがて種たちの体の中にメキメキと不思議な力がわいてきました。彼らはなんともいえない気分になって、しあわせでした。そうです。生きている者はすべて、自然と矛盾しないでいるとき、幸せなのですから・・・。彼らの新しい世界での希望はかなえられそうです!
しかし私たちが、けっして見落としてはならない一粒の種がここにあります。それはときどきあることですが、花壇に種がまかれたとき、あやまって花壇のかたわらのじゃり石の道に落とされた種です。
じゃり石の地、彼はそこに根をおろし、成長してゆかなければなりません。はたして彼はうまく育つのでしょうか? そうして、うまく花を咲かせることができるのでしょうか? 一粒の種は、花壇の種たちのようにそっと土をかぶせてもらうことはありません。また、ていねいに水を注いでもらうこともありません。冷たいじゃり石の道に転がったまま、ほうっておかれたのです。このお話は、この一粒の種のお話なのです。
「暖かい光よ、大地よ、水よ
ぼくたちは、君たちをたたえよう!
ぼくたちに、こんなにも元気を
希望を与えてくれたんだから・・・」
花壇の種たちはこころのなかで、歌いました。
「紙ぶくろのなかの仲間たち」と、じゃり石道の一粒の種はいいました。「君たちはしあわせ者だったね。けれど、ぼくのあすのいのちは、どうなるんだろう? 生きている者にとってそれ以上の恐怖はないよ・・・・・」
しかし、花壇の種たちはいいました。
「おまえひとりだけ、なにをグチっているのかね? ぼくたちを見習うがいい。ぼくたちは、光を、大地を、水を、そうだ、あらゆる大自然をこんなにも賛えているのだ! すべて健康な心は、感謝と賛美ということを知っている!」
「そうだ、こころには感謝。くちびるには賛美を、だ!」と別の種がいいました。
「もっともなことだ。でも、やはりぼくのあすのいのちはわからない!」と、一粒の種はつぶやきました。
「わからないやつだなあ。グチをこぼしたいヤツはこぼしているがいい。それは自らをいやしめるばかりだ。真にかしこい者は感謝ということを知っている!」
「もっともなことだ」と、一粒の種がいいます。「でも、やはり、ぼくのあすのいのちはわからない!」
花壇の種たちは、もはや一粒の種の「兄弟」ではないようです。花壇の種たちには、もう、一粒の種のこころを理解することはできませんでした。
花壇の種たちは、「もう、あいつのことはかまっていられないよ。ほうっておこう」といいました。
一粒の種の上高くを、小鳥たちがとおりすぎてゆきます。小鳥たちはどこまでも自由に空を飛ぶことができて、たちまちお隣の屋根のむこうに見えなくなりました。
「あの小鳥のように、どこまでも自由になんて多くは望まない。ただ、花壇までの10センチでいいんだ。ぼくに動くことができたら・・・」
どこまでもまっすぐに飛んでいく小鳥たちを見上げて、
「お〜〜〜い!」と、一粒の種は思いっきり叫んでみました。しかし、その声は空高くを飛んでゆく小鳥たちにはとどきません。
「あわれなるは、地にふす者だ・・・」
しかしある日、一羽の小鳥が一粒の種のすぐそばに舞いおりたのです。そこで彼はさっそく小鳥に頼みます。
「ねえ、小鳥さん。わるいけどそのクチバシでちょいとぼくを花壇にまで運んでくれないかね?」
「だけど、おいしそうな君だね。ぼくは君をくちばしにくわえたとたん、グイとひとのみして食べてしまいたくなるかも知れないよ」
「え〜〜〜っ!!」一粒の種は困りました。
「ぼくを信じることができるかね?」と小鳥はいいます。
「え〜っ、ぼくをのみこむのか、のみこまないのか、どっちなのか言ってよ」
「そんなこと、ぼくにもわからないよ。それでもぼくに頼むかね? 信じるとはそういうことなんだ」
「う〜ん。困ったなあ・・・」と、一粒の種は考えこんでしまいました。
「ぼくは、迷っている君につきあってるひまはないよ。ぼくだって生きていくことに必死なんだ。せめて君を食べないことをプレゼトとしておいてゆくよ。バイバイだ」 こう言って、小鳥はふたたび飛び立ちました。
「ま、まってくれよ、小鳥さん! ぼく、思い切って君を信じるから・・・」
「もういいって。信じるというはね、当てモノじゃないんだ。光のように、ただ真っ直ぐなものなんだ。選択じゃないんだ。他人を信じることができないのなら、あとはもう自分のことは自分でさ!」
小鳥は、アッというまにお隣の屋根のむこうにきえてゆきました。
“信じるということは、光のようにただ真っ直ぐなもの。”
この言葉は、その後も一粒の種の心からきえさることはありませんでした。
小鳥が飛び去ってしまっても、幸福者たちは彼にとりあわなくても、一粒の種の上には天から雨がふりました。雨に流されて、彼はコトコトと石のあいだをくぐりおり、やがてしっとりぬれた土に到着したのです。そうして、ようやく彼はそこに根をおろすことができました。
花壇の種たちの上には、朝夕、水が注がれました。また彼らの住んでいる土のなかには石ころなんてまじっていませんでしたし、彼らが育つのに適した栄養がありあまるほどに与えられていました。こんなぐあいでしたから、花壇の花たちは4、5日もすればみな、元気にみちた若芽を土の上にのぞかせたのです!
しかし、一粒の種の落ちたじゃり石の道には、いっこうに芽らしいものは見あたりません。一粒の種はどうなったのでしょうか? やはり、息たえてしまったのでしょうか?
いいえ、いいえ、彼はいまじゃり石の下で大変な戦いをまじえているところでした。というのは、彼がのびてゆこうとする頭上に大きな石がつかえていたわけです。「なにくそ、のびてやるぞ!」 彼は石を押しのけようと、暗く冷たいじゃり石の下でひとり格闘をつづけていました。けれども、1、2、3、4日過ぎても、5日過ぎても、彼は石を動かすことができません。1週間ガン張ってもダメでした。彼は疲れはててひとりつぶやきます。
「ぼくの努力なんてまったくむなしいよ。環境だ! 生きものは、どうせ運命からくる環境に支配されてしまうのだ! のびるのなんてもうやめたよ、バカバカしい!」
しかし、その考えはあまり長つづきしません。というのは、彼の頭はこう考えても、彼のすなおな心は賛成しなかったからです。心は彼にいいました。
「努力をあきらめる? それはとりもなおさず、いのちをあきらめるということじゃないのか。なんとさびしいことなんだ! 生きている者にゆるされることではないね。なんとしても、広い大空めざしてグングンのびてゆかなければならないんだ。少なくとも、そう努力しなければならないのだ!」
「なぜだ?!」と彼の頭がたずねます。心は答えます。
「理くつはない。理くつをこえて・・・ぼくは輝く太陽に引力を感じる! やはり輝く引力を! それが生きものの姿だ!」
「うん、そうだな」
彼はつぶやくと、またひとりぼっちの戦いをはじめました。
さて、花壇のアサガオたちは一日また一日、勢いよくのびてゆきました。すぐ彼らのかたわらには、いく本もの竹づえが立てられます。アサガオはめいめい与えられた竹づえにつるを巻きつけ、大空に向けて生き生きとのびてゆきます!
4日、5日が過ぎ去ります。
しかし、じゃり石の道にはやはり芽らしいものは見あたりません。一粒の種は、また別の石に頭を押さえつけられていたのです。
しばらくして彼は、はっきりといいました。
「やめたよ。もう努力なんてやめだ、バカバカしい! こんな大きな石があといくつつづいているか知れたものじゃない。けっきょく、じゃり石の道に落ちたのが運のつきさ!」
「そうよ。努力といったってね、さいげんなく努力するなんてことできっこないわ。ことに弱い地球の生き物たちにはね。もうおよしなさい、バカっ正直は! それよか、あんたあたいところに来ないこと?」 こういったのは、ケバケバしい金赤色の毛皮を着たモグラでした。「あんたも、あたいも、どうせこのヤミの世界から抜け出すことはできないのよ。宿命よ。宿命にさからうって手はないわ。おにいさん、かわいいわね。気に入ったわ。二人して、ヤミの世界で愉快な愉快な日々を過ごしましょうよ」
「ヤミの世界の愉快な日々って、どんな日々なんだね?」と一粒の種がたずねます。
「死んだ虫ケラのリンのほのおに照らされながら、歌って踊ってキャッキャッと笑って、すべてを忘れ去って楽しくくらす日々よ」
「ふーん。でも、そのあげく、ぼくのいのちはどうなるんだね?」
「青ぐされて死んでゆくわ。しかたないわね・・・」
「いやだ!」と一粒の種は飛び上がってさけびました。「青ぐされて死ぬなんて!」
「では、なんとかなるとでもいうの?」と、金赤色の毛皮のモグラがいいます。
「おまえさんのいうことはけっきょくまっ暗けだけど、それも真実かも知れないな。せめてくさって死ぬまでの短いいのちをせいいっぱい抱きしめて楽しくくらすとしようか」
「そうなさい。どうせ上の世界には住めっこないひとりぼっちよ、あんたは。あたいもそうよ。そんなひとりぼっちとひとりぼっちが体あたため合って、くさった枯れ葉のお料理を食べながらカン高く笑いながら死んでゆくのよ」
「うん、そうするよ」
一粒の種の頭上の石。そのために彼がのびるのをあきらめてしまった石。しかし、彼にとってこれが最後の石だったのですがね・・・・・・・
ちょうどこのころ、花壇に生まれたアサガオたちは竹づえにそって高くのび、たくさんのつぼみをつけました。
そうしてある朝、それぞれに赤、青、紫色の花を美しく咲かせたのです。すずしい朝のそよ風が、「おはよう!」とあいさつをして、花びらのあいだをとおりぬけてゆきます。アサガオたちは花びらをひらひらとなびかせて、おたがいに美しさを競い合いました。
「うむ、みんななかなかやるもんだねえ。なに、ぼくだって負けるものか!」
「なんてったって、わたしが一番美しいんだわ! わたしはこんなにすばらしい赤い花をもっているんですもの!」
「赤! なんて品のない色なの! それにくらべて、わたしのむらさきの花は!」といったぐあいでした。
赤い花は赤い花で、むらさきの花はむらさきの花で、それは個性というもので、それぞれが美しいのですがね。
こうしたある朝、あのじゃり石のあいだに、ふと、一つのみすぼらしいみどり色の芽が顔をのぞかせました。なんの芽でしょうか?‥‥‥そうです、これはまちがいなく一粒の種の芽です! 彼は金赤色の毛皮を着たモグラのところにはゆかず、気をとりなおしてひとりぼっちで戦ってのびてきたのです!
しかし、じゃり石のあいだに生まれた彼の戦いは、まだつづきます。彼には竹づえが与えられません。ですから、この子がほかのアサガオたちのようにうまくのびてゆくことができなかったとしも、無理はありません。彼は地をはい、細い雑草にしがみついてみました。しかし、雑草は3日もたたないうちに、ふとした風でもろくも倒れてしまいました。彼もろともに! つえをなくした彼は、自分自身のつるにつるを巻きつけてみました。しかし、それはどうにもならないことです。行先はまたあの地下にすぎないのですから・・・ 彼はあわててそのつまらないあやまちを中止しました。
一粒の種はなににつけても恵まれていない自分を悲しみました。しかし彼の心はちょっぴり成長していて、彼はいいます。
「悲しみもまた恵み。恵みには二つあって、プラスの恵みとマイナスの恵みがあるんだ。弱いぼくたちはプラスの恵みのほうがうれしいけれど、生きている者は自分に与えられたそれら二つの恵みを生かして、“自分色の花”にたどりつかなければならないんだ。悲しんでいるひまはないぞ!」
彼は体をうちふるわせながらこういいましたが、彼の“自分色の花”を咲かせるという願いはかなえられないままに、3日が過ぎ、5日が過ぎ、1週間が過ぎ去ります。しかしやはり花は咲きません。
8日めの夕方から付近いったいに大雨が降りはじめました。雨は夜になってもやみません。暗ヤミを破ってストロボフラッシュのような稲妻が光り、カミナリがゴロゴロと大地をふるわせました。そのたびにガラス戸がガタガタと鳴って、おとなでさえも怖くなるような夜でした。小さな子どもたちは自分の寝床をあわててぬけ出し、おとなたちのフトンのなかにもぐり込んで耳をふさぎました。けれど一粒の種のアサガオは雨にたたかれながらヤミのなかで花を開こうとけんめいの努力をつづけていました。
「生きている者はみんな、プラスの恵みとマイナスの恵みをつなぎ合わせて“自分色の花”を咲かさなければならない! “自分色の花”を咲かさなければならない!」
ピカッ、ゴロゴロゴロ!
「“自分色の花”を咲かさなければならない!」
ピカッ、ゴロゴロゴロ!
彼は、しずかな戦いを戦うひとりぼっちの戦士でした。敵は不運な環境です。自分自身の弱さです。彼だってこんな夜にはおかあさんを呼びたかったにちがいありません。そのふところに抱かれて、小さく縮んでいたかったにちがいありません。しかし、彼のおかあさんはもう、去年の夏の終わりにこの世を去っていました。
ようやく明け方近くになって、雨があがりました。カミナリがしだいに遠ざかってゆきます。そうして、重たくたれこめた雲のむこうに朝日がさしはじめたころ、一粒の種のアサガオはつるのなかほどに一輪の小さな小さな、うすむらさき色の花を咲かせたのです!
じゃり石の道に落ちた種だって、花を咲かせることができました!
まもなく、人々がこの庭園におりてきて、朝の空気を胸いっぱい吸い込み深呼吸をします。
「ゆうべはひどいあらしでしたねえ」と一人がいいます。
「あんなにうるさくてはねむれないよ! ねぶそくだ。ねむい、ねむい!」
そうして人々は花壇に近づいていいました。
「なんて立派に咲いた花たちだろう。あらしを乗り越えて!」
「アサガオたちもこんなすがすがしい花を開くには、きっと多くの苦難を乗り越え、努力を重ねてきたことだろう。しかし、あらしが過ぎ去ったあくる朝には大輪の花を開くのだ!」
「そうですわ。私たち人間の場合と同じようにね」
「君もぼくも、そんなふうに二人の花を咲かせようね」と若い青年が若い女のひとにいいます。
しかしそのとき、一粒の種のアサガオは、一人の男が自分の小さな花をゆびさしてこういうのを聞きました。
「けれどそれにくらべて、この花をごらん。まるで破けたチリ紙のような、このみすぼらしい花を!」
「ほんとうだ。なんとできのわるい花だ! なまけるとこうなる、人間も!」
「なまけるとああなる!」と花壇の花たちも声をそろえていいました。
「恵みにはプラスの恵みとマイナスの恵みがある。そのことはわかっている。だけど、ぼくはいま口惜しいよ!」 がまん強い一粒の種のアサガオからはらはらと露のなみだがこぼれました。
じゃり石の寝床
注がれない水
あすのいのちがわからないという恐怖
飛び去った小鳥
ゆくてをふさぐ石
金赤コートのモグラのヤミの世界への誘惑
与えられない竹づえ
あらし
これまでたえてきたあれこれがどっと思い出されてきて、あとからあとからなみだがあふれ出てとまりません。ほんとうにがまん強い者にこそ、はげしく、胸の底から泣かないではいられないときがあるのです! 彼の暗ヤミのなかのひとりぼっちの戦いのことを知っている者は、だれ一人いません。それを想像してみようとする者さえありませんでした。
彼の花はみすぼらしい小さな花です。しかもたった一輪です。
それでも、花はつるに咲いています。つるは、土から生えています。たとえつるがどんなに長くても、つるをたどってゆけば彼が生えてきた土地がわかるはずです。しかし人々は結果ばかりを見てしまいます。ルーツをたどってみようとする人はほとんどいません。それが“人々”というものなのでした。
やがて、一粒の種のアサガオは露のなみだをはらってつぶやきました。
「一切の戦いのことは自分自身の胸の内に! ぼく、胸を張ってつぶやくよ。この小さなうすむらさきの花こそが、ぼくの“自分色の花”輝きなのだ」
朝の一筋の光がいいました。
「そうだ。花は大輪ばかりが輝くのではない! 真に輝くのは、祈りのようにもっと内なるもの。 そう、自分自身への深い信頼を友達にして……ね」
それから、一粒の種のアサガオは思いました。自分もまた他人のルーツのつるをめったにたどっていないことを……。知らないあいだに、他人にひとりぼっちの悲しみを与え続けているのかも知れないことを。
| |
 ◆「こころの時代」シリーズ14◆
UP H16・4・1
◆「こころの時代」シリーズ14◆
UP H16・4・1
 ◆「こころの時代」シリーズ14◆
UP H16・4・1
◆「こころの時代」シリーズ14◆
UP H16・4・1